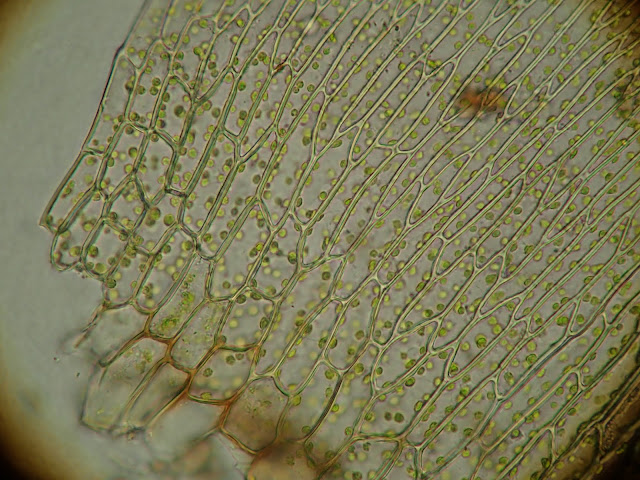奥多摩の山地林内の腐木に生えていました。
確信はありませんので、ご注意ください。
生えている雰囲気はナガヒツジゴケに似ているように思いました。
蒴柄は平滑で、毛尖なのは間違いないと思います。
ハネヒツジゴケは蒴柄にパピラがあって、基本的に鋭尖頭なのではずれます。
縦皺はほとんどないと判断しました。
そうなりますと、深い縦皺があるはずのナガヒツジゴケははずれます。
ヒモヒツジゴケとは以下の点で違うと思いました。
この個体は、葉身は三角状卵形、葉身上部は漸尖している、お椀状は顕著ではない、葉身細胞は幅広くない、葉身上部に鋸歯なし、枝はあまり立ち上がらない。
葉身中部の細胞は75~85μmほどもあり、図鑑の記述よりもかなり長いです。
キヌヒツジゴケも結構合いますが、関東に記録がなく、出しにくいです。
写真1:腐木に群生
写真2:生育状況
写真3:生育状況
写真4:蒴の様子
写真5:全形
写真6:全形。古い枝と新しい枝で色が違います。
写真7:
写真8:
写真9:茎葉の方が少し幅広か
写真10:枝葉と茎葉の大きさはほとんど同じ?
写真11:蒴柄は平滑
写真12:茎葉
写真13:茎葉
写真14:葉身下部
写真15:葉身下部の細胞
写真16:葉身中部
写真17:葉身中部の細胞。75×6μmほどありました。
写真18:葉身中部の細胞。85×6μmほどありました。
写真19:葉身上部。ほとんど全縁のようです。
写真20:葉先